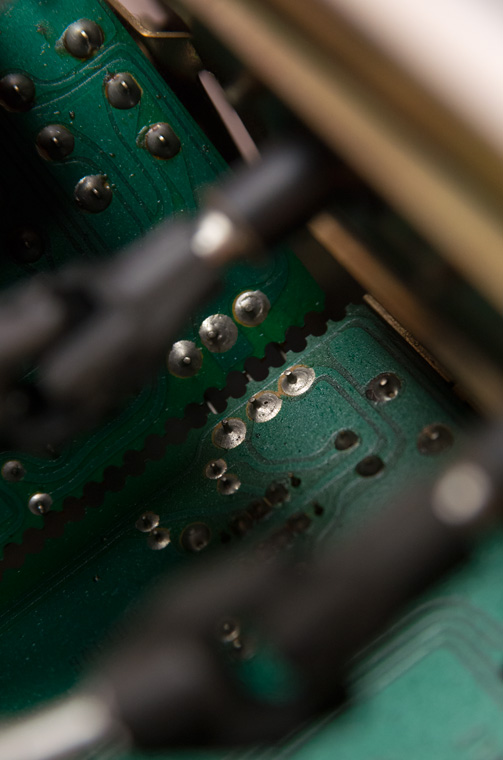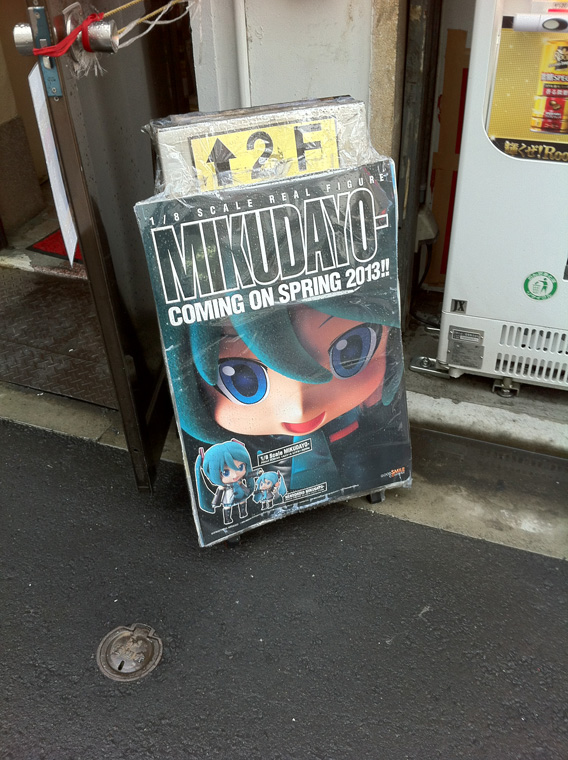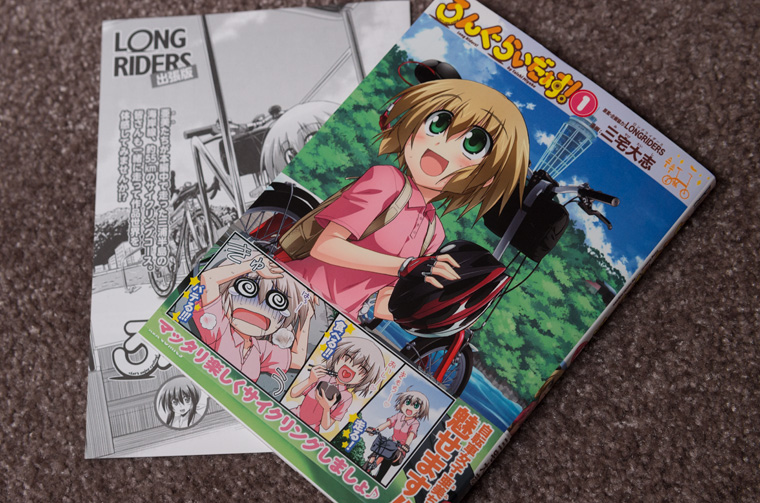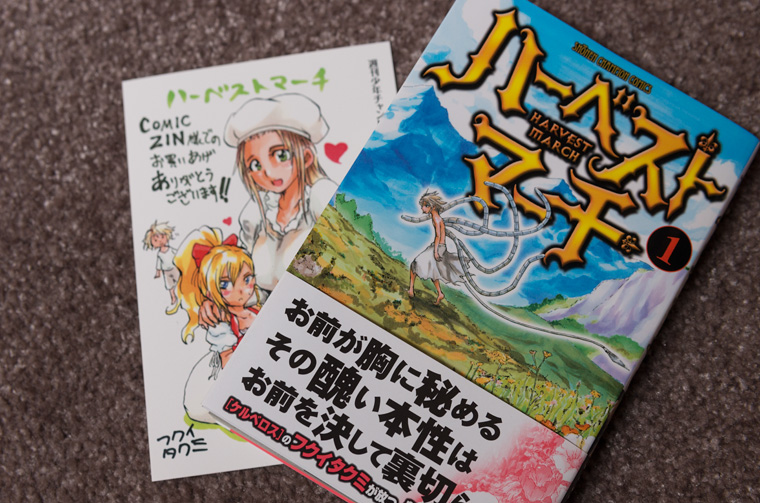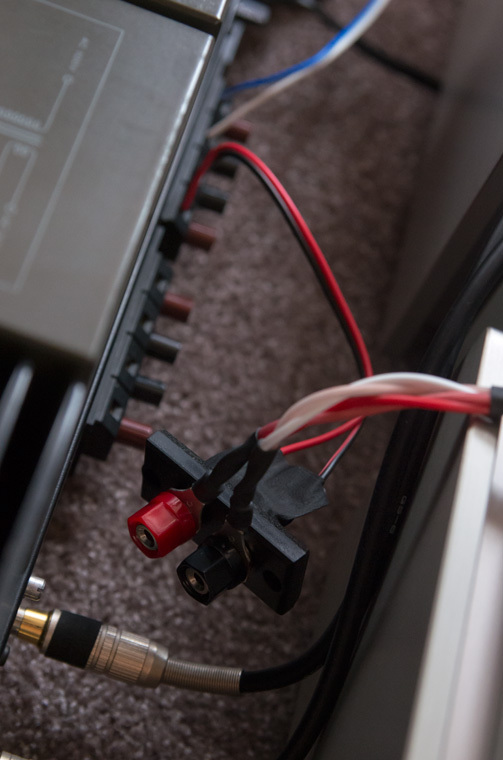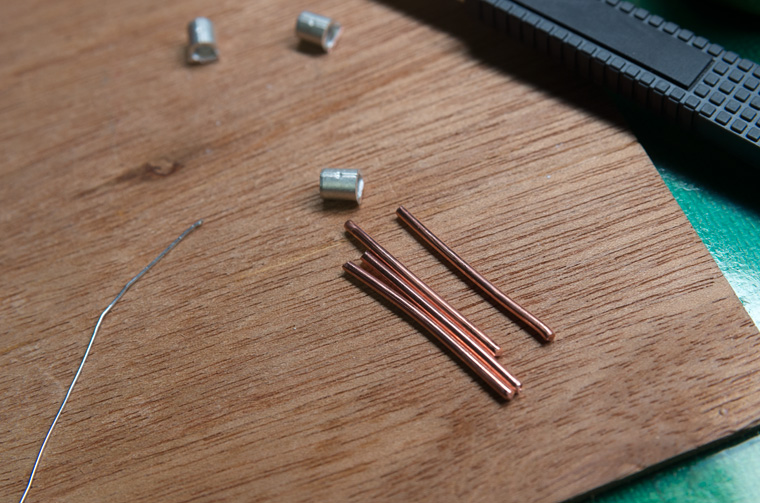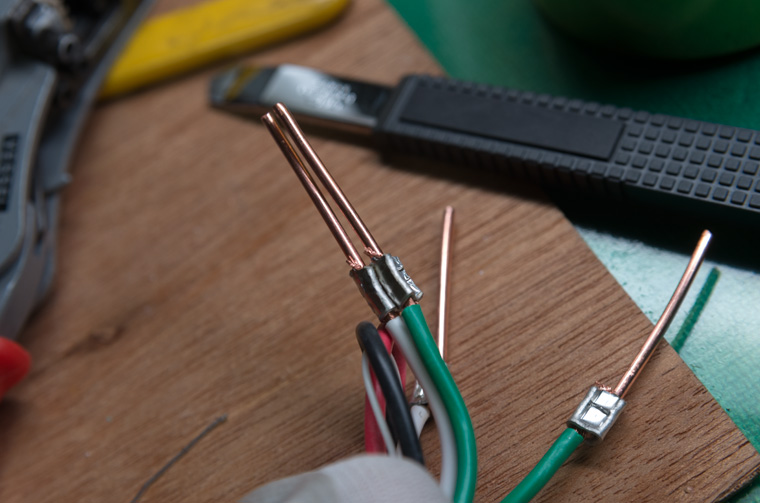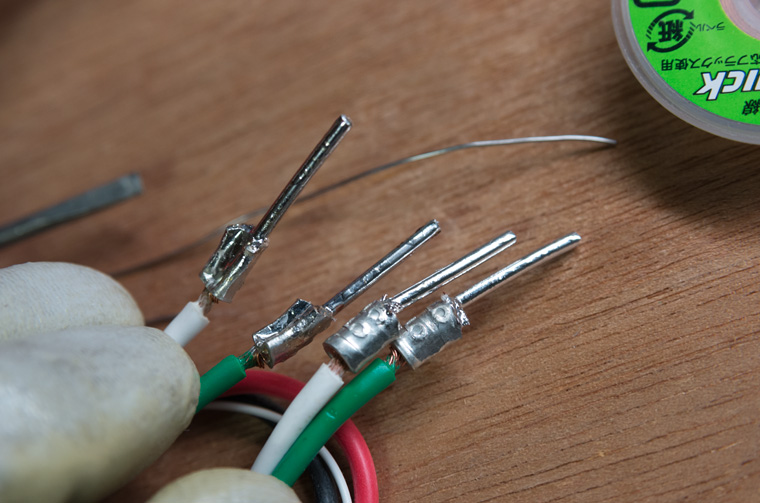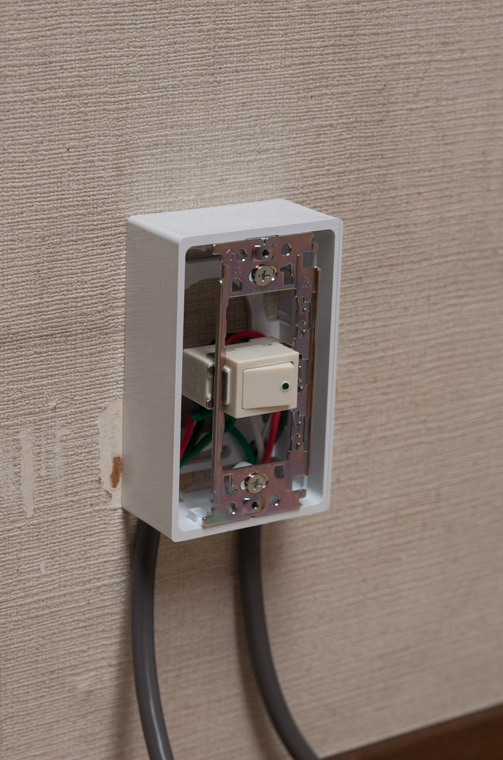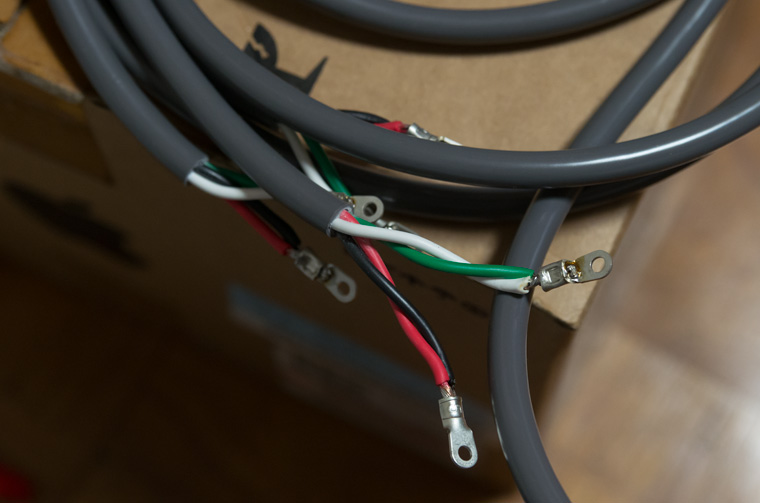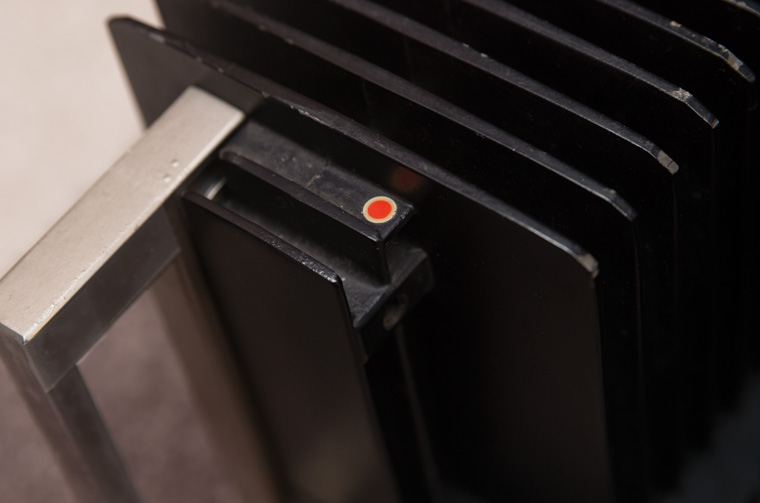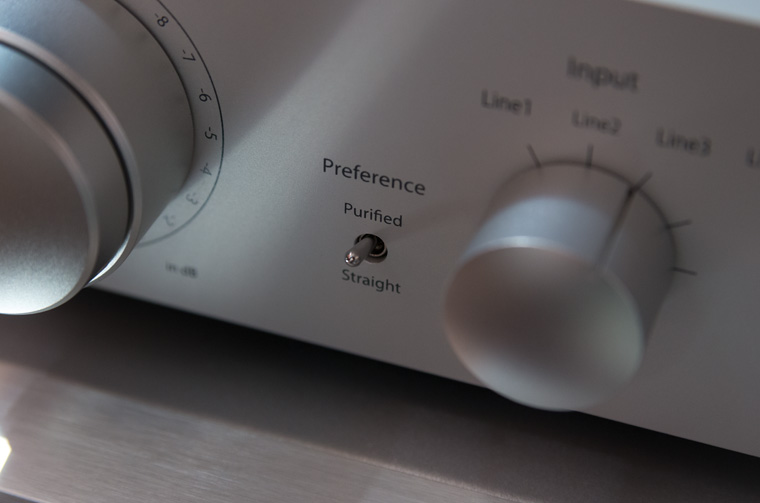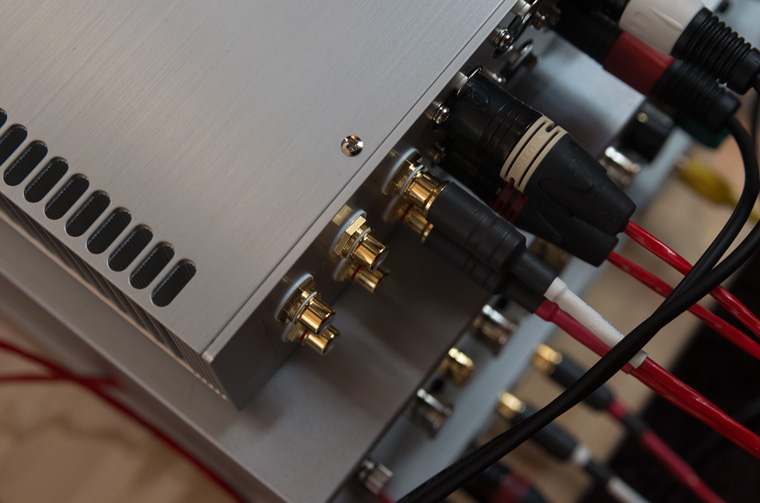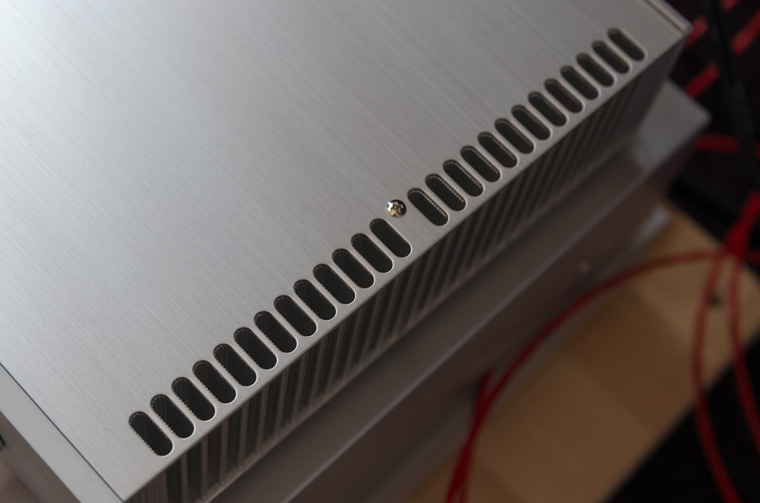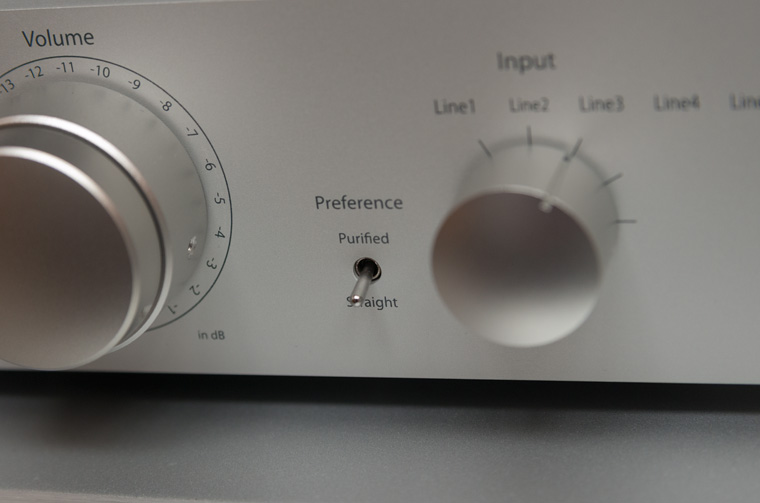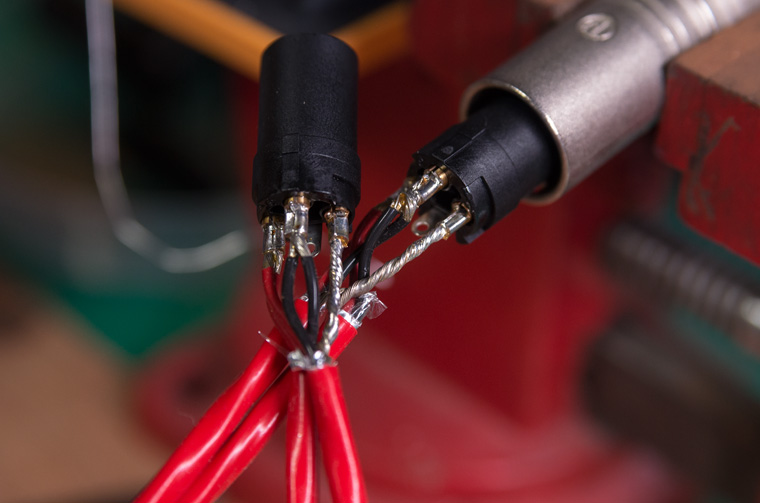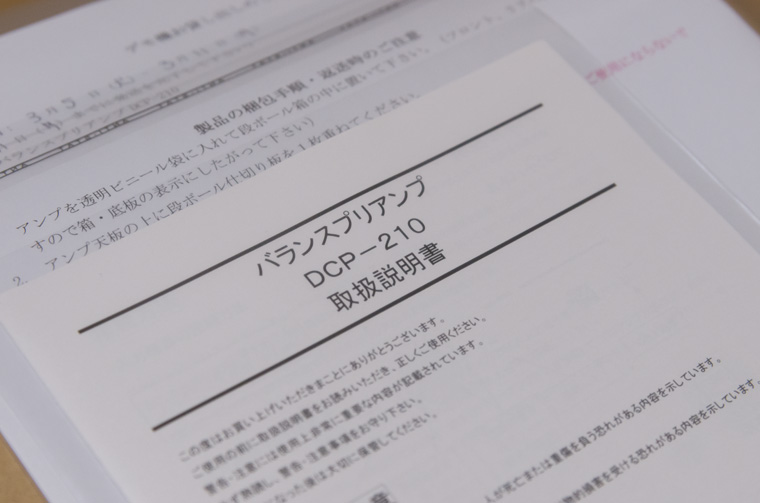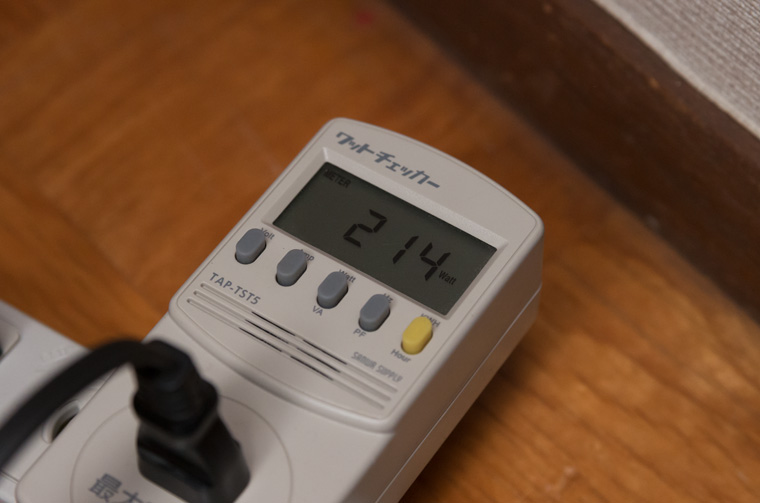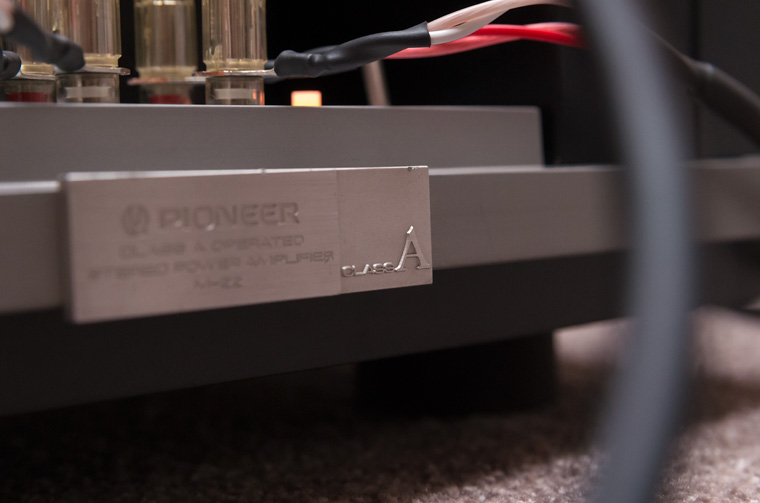Note
链て saga audio photo bicycle cat 花淡
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2005钳 | 10奉 11奉 12奉 | |
| 2006钳 | 01奉 02奉 03奉 04奉 05奉 06奉 07奉 08奉 09奉 10奉 11奉 12奉 | |
| 2007钳 | 01奉 02奉 03奉 04奉 05奉 06奉 07奉 08奉 09奉 10奉 11奉 12奉 | |
| 2008钳 | 01奉 02奉 03奉 04奉 05奉 06奉 07奉 08奉 09奉 10奉 11奉 12奉 | |
| 2009钳 | 01奉 02奉 03奉 04奉 05奉 06奉 07奉 08奉 09奉 10奉 11奉 12奉 | |
| 2010钳 | 01奉 02奉 03奉 04奉 05奉 06奉 07奉 08奉 09奉 10奉 11奉 12奉 | |
| 2011钳 | 01奉 02奉 03奉 04奉 05奉 06奉 07奉 08奉 09奉 10奉 11奉 12奉 | |
| 2012钳 | 01奉 02奉 03奉 04奉 05奉 06奉 07奉 08奉 09奉 10奉 11奉 12奉 | |
| 2013钳 | 01奉 02奉 03奉 04奉 05奉 06奉 07奉 08奉 09奉 10奉 11奉 12奉 | |
| 2014钳 | 01奉 02奉 03奉 04奉 05奉 06奉 07奉 08奉 09奉 10奉 11奉 12奉 | |
| 2015钳 | 01奉 02奉 03奉 04奉 05奉 06奉 07奉 08奉 09奉 10奉 | |
| 2016钳 | 09奉 | |
| 2019钳 | 04奉 06奉 07奉 08奉 09奉 10奉 11奉 12奉 | |
| 2020钳 | 01奉 02奉 03奉 04奉 05奉 06奉 07奉 08奉 09奉 10奉 | |
| 2021钳 | 01奉 10奉 | |
| 2022钳 | 01奉 | |
| 2023钳 | 01奉 05奉 07奉 09奉 10奉 | |
| 2024钳 | 01奉 09奉 | |
| 2025钳 | 01奉 04奉 09奉 |
top